








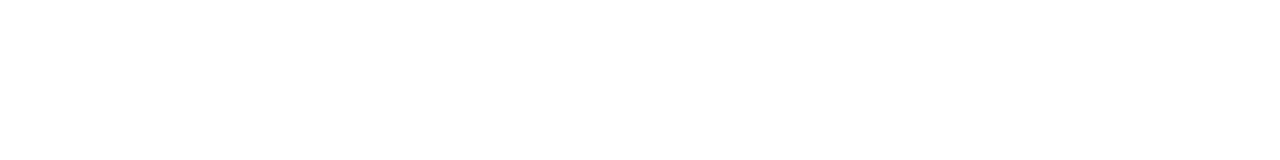
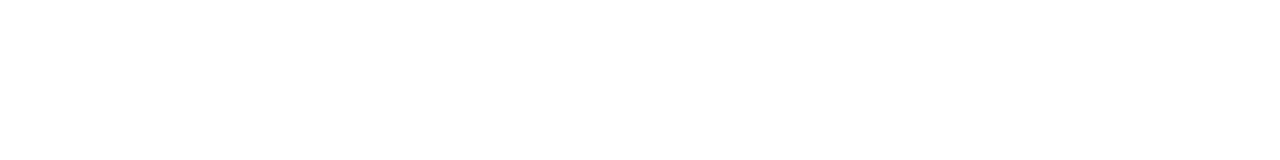
つかみかけていた夢が、一瞬にして消えていった――。1993年10月28日、カタール・ドーハの地で起きた出来事は、日本サッカー界にとって、まさに悲劇と言えるものだった。
いわゆる「ドーハの悲劇」として記憶されるFIFAワールドカップアメリカ大会アジア最終予選。あの時、あの地で一体何が起きたのか。オフトジャパンの主軸を担った福田正博さんに、当時を振り返ってもらった。

©JFA/PR
1993年当時、日本は空前のサッカーブームに沸いていた。同年5月15日にJリーグが開幕するのに加え、前年のアジアカップで優勝を飾ったこともあり、ワールドカップアジア予選に臨む日本代表には、日本中からの大きな期待が集まっていた。
「あの頃は、本当に凄かったですね。92年に初めて東アジア(第2回ダイナスティカップ)でチャンピオンになって、そのあとに第10回アジアカップ広島でも頂点に立った。ワールドカップにはじめていけるんじゃないかという空気が、世の中には蔓延していたと思います」
そう語る福田さんをはじめ、当時の日本代表の選手たちの胸の内にあったのは、この盛り上がりを一過性で終わらせてはいけないという使命感だった。
「選手の立場とすれば、Jリーグがスタートしても、その先どうなるかは分からなかった。ふたを開けたらものすごくブームになったけど、これをブームじゃなくて、継続した人気にしていかなければいけない。そのためにはワールドカップに出る必要がある。そういう強い想いが日本代表の選手たちにはありました」
当時のチームを率いたのは、オランダ人のハンス・オフト監督。史上初となる外国人指揮官が1992年に就任にすると、同年夏に韓国、中国、朝鮮民主主義人民共和国と争った第2回ダイナスティカップでいきなり優勝。11月には広島で開催された第10回アジアカップも制し、日本は一躍、アジアの強豪の仲間入りを果たしたのだった。

©AFLO
「僕の人生を大きく変えてくれた方ですね」と、福田さんはオフト監督に感謝の想いを隠さない。
「サッカー観を変えてくれた。難しいことを一切言わないし、言っていることが分かりやすかった。なかでもオフトが僕らにもたらしてくれたのは、自信ですよね。彼の考え方は、ないものを探すのではなく、あるものを最大限に生かせというものでした」
例えばフィジカルや個人能力で韓国にかなわないのであれば、技術や組織力で対抗すればいい。相手の得意とする場所で勝負するのではなく、自らの特長を最大限に生かすやり方で、日本は着実に力をつけていった。
年が明け、1993年4月にワールドカップアジア1次予選が幕を開ける。タイ、バングラデシュ、スリランカ、UAEと同居したこのグールプを1位通過すれば、10月からの最終予選へと進出できるレギュレーションだった。
力関係を考えればUAEがライバルとなりそうだったが、福田さんは初戦で対戦したタイとの一戦が最も苦しかったと振り返る。
「初戦は、もうガチガチでしたね。なぜかと言うと、今の日本代表が置かれている立場になったんですよ。つまり、勝って当たり前という状態ですね」
それまでの日本は、あくまで下から追い上げるチャレンジャーの立場だった。ところが、前年にアジアを制したことで他国の警戒が強まるだけでなく、日本中を包み込んだ「はじめてワールドカップに行ける」という空気が、特大のプレッシャーとして選手たちを襲ったのだ。
「それまでは、そこまで期待感はなかったので、失うものがない中でやっていましたよ。でもアジアの頂点に立って、しかもこれからJリーグが始まる。何としてもワールドカップに出なければいけない。使命感の一方で、とてつもない重圧が僕たちにのしかかっていました」
結局、タイには苦しみながらも1-0で勝利。福田さんも三浦知良選手の決勝ゴールをアシストする活躍だった。ところが、福田さんはこの試合のことをほとんど覚えていない。
「アシストしたこと以外、なにも覚えないんですよ。あと、空回りしていたことは覚えています(笑)。人間、緊張するとああいうふうになってしまうんだなと。気持ちと身体が一緒にならなかった。当時の僕には、あれほどの重圧をコントロールできる経験値がなかったんです」
もっとも初戦を乗り切った日本は、その後、バングラデシュ、スリランカ、UAEに連勝。UAEに舞台を移した二回り目の対戦も(当時はホーム&アウェイ方式ではなく、日本ラウンド、UAEラウンドのダブルセントラル方式で行われた)危なげなく勝利を重ね、7勝1分という成績で最終予選進出を決めた。
1次予選が終わると間もなく、Jリーグが開幕。空前のサッカーブームが到来し、選手たちは一躍、スターダムへとのし上がっていく。しかし、まばゆいばかりのスポットライトが当たる一方で、日本代表の選手たちの肉体は着実に蝕まれていった。

©JFA/PR
当時のJリーグは、週2ペースで行われ、しかも延長Vゴール、さらにはPK戦のルールまで採用されていた。「これはもう、今考えると殺人的なスケジュールですよ」と、福田さんも苦笑いを浮かべる。
「PKまであるから、試合がいつ終わるかわからない。だから遠征に行ったときに、帰りの新幹線を予約できないんですよ」
Jリーグのスケジュールの合間には日本代表の活動もあった。「浦和に引っ越してから、ほとんど家にいなかったほど」と福田さんが振り返ったように、当時の日本代表の選手たちは、過酷な日程を強いられていたのだ。
アジア最終予選を10月に控え、日本代表は9月にスペイン遠征を実施している。そこでは地元クラブとの練習試合をこなしたが、福田さんには厳しい練習をした記憶がない。
「のちにオフトに聞く機会があったんです。『なんで、あの時にスペインに行ったのか』って。そしたらオフトは『トレーニングに行ったんじゃない。バカンスに行ったんだ』って答えたんですよ。それくらい、あの時の選手たちは疲れていたんです」
高まる期待感のなか、実情は不安も付きまとっていた。日本代表は満身創痍のまま、最終決戦の地、ドーハへと向かって行った。