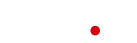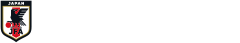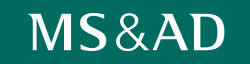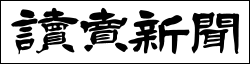ニュース
【Match Report】SAMURAI BLUE、上田綺世選手の終了間際のゴールでパラグアイ代表と2-2で分ける
2025年10月11日

SAMURAI BLUE(日本代表)は10月10日(金)、大阪のパナソニック スタジアム 吹田にて行われたキリンチャレンジカップ2025でパラグアイ代表と対戦。終盤交代出場した上田綺世選手(フェイエノールト)の試合終了直前のゴールで追いつき、2-2で引き分けました。
日本代表は次戦、10月14日(火)に東京スタジアムにてブラジル代表と対戦します。
来年のFIFAワールドカップ26へ向けてチーム強化を図る日本が、堅守で南米予選を突破したパラグアイにリードを許しながら2度追いつき引き分けに持ち込みました。
日本は3-4-2-1のフォーメーションで、先発には小川航基選手(NECナイメヘン)を1トップにゲームキャプテンの南野拓実選手(ASモナコ)と堂安律選手(アイントラハト・フランクフルト)を2列目のシャドー、両ウィングには右に伊東純也選手(KRCヘンク)、左に中村敬斗選手(スタッド・ランス)を起用。佐野海舟選手(マインツ05)と田中碧選手(リーズ・ユナイテッド)がボランチを組み、最終ラインは右から瀬古歩夢選手(ル・アーヴルAC)、渡辺剛選手(フェイエノールト)、鈴木淳之介選手(FCコペンハーゲン)を並べ、GKは鈴木彩艶選手(パルマ・カルチョ)という顔ぶれで臨みました。

9月のメキシコ、アメリカとの2試合を無得点に終わっていた日本は、ゴールへの意識も高く、序盤から積極的に仕掛けて相手ゴールに迫ります。
一方、パラグアイは南米予選突破を決めた9月のエクアドル戦の先発メンバーを軸に4-2-3-1の布陣で、ブロックを作って守備を固めながら、MFミゲル・アルミノン選手やMFディエゴ・ゴンサレス選手、FWアントニオ・サナブリタ選手らを中心に、日本の守備陣の裏のスペースを狙ったパスを多用して攻撃を仕掛けます。
前半21分の先制点もその一つでした。中盤でパスを受けたダミアン・ボバディジャ選手が日本最終ラインの裏へロングパスを送り、アルミノン選手が日本守備陣の裏を取って左足で受けてコントロール。即座に体勢を整えると左足で捉えてゴールネットを揺らしました。
しかし、日本もすぐに反撃します。失点から5分後、高い位置でボールを奪うと佐野選手が小川選手へパス。受けた小川選手は鋭く反転して強烈なミドルシュートを放ち、同点ゴールを決めました。

日本はその後もコンパクトに保って相手にプレッシャーをかけ、大きなサイドチェンジからボールを持った伊東選手が右サイドで堂安選手との連係を使って相手を揺さぶり、左サイドでは6月のアジア最終予選のインドネシア戦以来の出場となった中村選手が切り込んで鋭いクロスをゴール前に送ります。
前半40分には、オフサイドにはなりましたが中村選手のクロスに相手DFの間を獲った小川選手が頭で合わせ、終盤には伊東選手のFKに堂安選手が足を振ります。後半序盤には、伊東選手のCKを小川選手がヘディングで狙いますが、いずれも相手GKの好守に阻まれます。その後も、堂安選手の右クロスに相手の裏に入った南野選手が体で押し込む場面を作りますが、これはオフサイド。日本が相手より多くチャンスを作ります。

しかし、再び均衡を破ったのはパラグアイでした。
64分、ディエゴ・ゴメス選手がDFファン・カセレス選手に預けてゴール前に入り、折り返しのクロスに頭で合わせ、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン所属の22歳の攻撃手が2-1としました。
その後、堅守を維持してカウンターを狙う相手に対して、日本は鎌田大地選手(クリスタル・パレス)、代表デビューとなった斉藤光毅選手(クイーンズ・パーク・レンジャーズ)、町野修斗選手(ボルシア・メンヘングラートバッハ)、相馬勇紀選手(FC町田ゼルビア)らを次々とベンチから送り込んで得点機を模索。83分には相馬選手のクロスに斉藤選手が頭で合わせますが、枠を捉えることができません。
試合時間が少なくなる中、日本は89分に小川選手に代えて上田選手を投入。すると、出場から5分後の後半アディショナルタイムでした。
相馬選手のFKを起点に右サイドへ展開し、相手のクリアボールを回収した伊東選手が、右サイドから相手GKとDFの間を狙った鋭いクロスを送ります。これに上田選手がファーサイドで反応。ダイビングヘッドで合わせて押し込み、再び同点として2-2で試合を終えました。

日本は3試合ぶりの勝利とはいきませんでしたが、南米の強豪に土壇場に追いつく粘りを見せ、複数得点により無得点試合は2試合でストップです。
なお、この試合ではキックオフ前に、今年8月に亡くなられた釜本邦茂元JFA副会長のご冥福を祈って黙祷が捧げられ、1968年メキシコオリンピック銅メダル獲得など日本代表歴代最多75得点の活躍をされた現役時代の思い出のスライドが場内のスクリーンに掲示されました。
監督・選手コメント
森保一 SAMURAI BLUE(日本代表)監督
ホームでサポーターの皆さんに、選手たちが今の自分たちよりもさらに強く、レベルアップして、勝利を目指して戦うための非常に素晴らしい雰囲気を作っていただきました。感謝します。
試合は失点を抑えながら先制点を奪う展開に持っていければと思っていましたが、それができず、2度リードされました。アグレッシブに戦いながらも守備では堅く守っていかないといけないと改めて感じています。サッカーで1失点はある程度は仕方ないところもあるかもしれませんが、複数失点は避けなければいけません。「いい守備からいい攻撃」という部分は、さらに磨いていかなければならないという結果になったと思っています。攻撃の部分では2点獲れたこと。なおかつ、得点を獲ったのがFWで、我々が点を獲ってほしいと思うポジションの2人でしたので、今後の戦いにおいて軸がしっかりすると思います。そこからチャンスの作り方、バリエーションを増やしていかなければいけないと感じています。
アジア予選終了後、アジア以外のチームと試合をして、やはりレベルの違いは感じている中で、アタッキングサードでさらにシュートチャンスまで繋げるところをやっていかなければならないですし、個人の部分でもチームの部分でもさらに得点を奪えるように、まずは得点チャンスを作れるようにチャレンジしていかなければと思っています。我々が押している時間が長かった中で、勝ち越しゴールを奪う力を、さらにつけていかなければいけない展開だったと感じています。
DF #25 鈴木淳之介 選手(FCコペンハーゲン/デンマーク)
相手の特長などを考えながらやりましたが、2失点が本当に悔やまれますし、潰しきれなかったのがすごく悔しいです。パラグアイは起点を作らせるとそこから展開するのが上手だったので、そういうところをしっかりカバーし合いながら、攻撃の芽を潰すところは潰すと意識しながらやっていました。(2失点目の場面は)もう少ししっかり潰せればよかったのですが、距離感の問題だと思います。1メートルのこだわりを持って、もっとやっていかないといけないと思います。
MF/FW #14 伊東純也 選手(KRCヘンク/ベルギー)
パラグアイも強い相手なので少し難しい部分もありましたが、何回かサイドからうまく崩して、堂安選手がクロスを上げたり、中村選手がシュートした場面もありましたし、それ以外にもショートカウンターがうまくいったところもありました。チャンスは前回に比べて多く作れたのではないかと思います。ただ、良くないシーンもあって、クロスからの失点が多いという印象なので、クロスの対応をしっかりと、マンツーマンでやっている分、相手に負けないというところはやらなければいけないと思います。
MF/FW #15 鎌田大地 選手(クリスタル・パレス/イングランド)
失点してからチームとして守備の部分がはまらずに良くなかったですし、難しかったです。相手が少し余裕を持ってボールを持つようになった時に、バラバラに奪いに行ってしまった感じがあります。チームの戦術というよりも、個人個人のデュエルで負けていたという部分が多かったと思うので、自分たちがやらないといけないと思います。守備が良くないと攻撃もうまくいきません。ただ、追いついたのはすごくポジティブです。こういう試合で負けるとチームの雰囲気も下がるところがあるので、点を入れて戻れたことは評価できる。次の試合にもそういう部分ではつながったと思います。
MF/FW #18 上田綺世 選手(フェイエノールト/オランダ)
噛み合っているなというのはもちろんありますし、今日は(ボールが)来ましたが、来ない時は来ないものです。今はその運も含めていい状態なのかと思います。終盤は時間もなくて、本当に点を取りに行ったシフトでしたが、それは本戦でも考えられることです。(18番をつけての初試合で得点して)特別うれしいです。普段から支えてくれる母と僕が憧れている父も来ていたので、点を獲って少し恩返しができたのが一番うれしい。次のブラジル戦も自分が与えられた時間の中で、得点もそうですが、チームに貢献するところを意識して、状況や空気を読んで自分に必要なことを最大限できたらいいと思います。
MF/FW #19 小川航基 選手(NECナイメヘン/オランダ)
今回の活動期間中、名波コーチから「振れるタイミングで振るように」と毎日のように言われ続けていましたが、それがあの瞬間に頭によぎって、そこですぐに振るという判断をできたのが大きいと思います。インパクトのあるシュートをいつも心がけていて、自分がシュートを打てる位置にボールをトラップできました。自分がCKやクロスからの得点が得意だとみんなが共通意識を持ってくれて、自分の良さをだんだんみんなが理解してきてくれたのかなと試合を通して感じました。
MF/FW #21 佐野海舟 選手(マインツ05/ドイツ)
守備から入ることは意識しましたし、相手の球際に負けずに、距離を詰めて受けさせないことを意識して入りました。気持ち的にも自分のできることをやろうと思っていましたし、ディフェンスラインの選手や周りの部分など、後ろから声かけがあったので、すごくやりやすかったです。競り合いそうな展開で失点してしまいましたが、そういう時にどれだけボランチとして、しっかり状況を見て把握してできるかというのは、まだまだ足りないなと思います。
グスタボ・アルファロ パラグアイ代表監督
異なるスタイルの2チームが対戦して、両チームにとって素晴らしい試合になったと思います。2022年のワールドカップの前にエクアドル代表を率いて日本と対戦しましたが、その時よりも日本はさらに進化を遂げていると感じました。日本の攻撃のトライアングルにはうまく対応できたと思いますが、後半の試合運びは難しくなりました。長時間の移動や時差でフィジカル面では万全でなかった影響もあって勝利できず、最後に同点にされて選手たちは非常に残念がっていました。ただ、選手たちはワールドカップの試合に匹敵するような真摯な姿勢で試合に臨みましたし、それこそが我々が選手に求めていることでもあります。
2025年10月10日(金) 19:20 キックオフ(予定) vs パラグアイ代表
会場:大阪/パナソニック スタジアム 吹田
大会情報はこちら
関連ニュース
-
日本代表
2025/10/10
【受付開始のお知らせ】「JFA's DREAMで行く! SAMURAI BLUE応援バスツアー」 11/14(金)開催

-
2025/10/10
令和6年能登半島地震復興支援活動 サッカーファミリー復興支援チャリティーオークション 2025年第7弾 Vol.1

-
日本代表
2025/10/10
【JFA STORE】新商品が続々登場!フットサルグッズや審判グッズも販売開始

-
日本代表
2025/10/10
チケット完売のお知らせ キリンチャレンジカップ2025 10.10(金) SAMURAI BLUE(日本代表)対 パラグアイ代表 @大阪/パナソニック スタジアム 吹田

-
日本代表
2025/10/09
パラグアイ代表 来日メンバー キリンチャレンジカップ2025 SAMURAI BLUE(日本代表) 対 パラグアイ代表【10.10(金)@大阪/パナソニック スタジアム 吹田】

最新ニュース
-
日本代表
2026/02/19
U-20日本女子代表候補 メンバー・スケジュール 国内トレーニングキャンプ(2.23-26 千葉/高円宮記念JFA夢フィールド)

-
日本代表
2026/02/19
ビーチサッカー日本代表候補 メンバー・スケジュール 国内トレーニングキャンプ(2.26-3.2 @沖縄/宜野湾市)

-
ビーチサッカー
2026/02/19
砂上のなでしこたち、沖縄に集結!「第8回BeachSoccer地域女子チャンピオンズカップ」3月7日(土)・8日(日) 沖縄県西原きらきらビーチにて開催

-
指導者
2026/02/18
2026年度 JFA エリートユースAコーチ養成講習会 開催要項

-
大会・試合
2026/02/18
【ホットピ!~HotTopic~】フットサル日本一を懸けた戦いがまもなく開幕